今日は、水彩画カリキュラムの第1回目 - 「重色あそび」です。
デッサンカリキュラムは30回目でミロのヴィーナスを完成させて、今日からは水彩画カリキュラムに突入しました。
1. 透明水彩
水彩絵の具には、「透明水彩」と「不透明水彩」の2種類があります。
透明水彩は、下の色が透けるため、みずみずしい表現になります(上のリンゴの左が透明水彩、右が不透明水彩)
水彩画カリキュラム第1回の今日は、透明水彩で色を重ねて遊ぶことから始めました。
生徒さんのサンプルはどれも鮮やかでお見事!
2. 水張り
まずは、水張りという作業からスタート
水張りは、予め紙をじゅうぶん濡らし、最大まで伸長させたところで、しっかりとした台に固定して乾かす作業です
水張りテープを使って4辺をパネルに固定して準備完了
絵の具はHOLBEIN(ホルバイン)という大阪のメーカー製
つるくびという水差しを使って絵の具を薄めて使います
これで準備完了!
3. 重色あそび
何かテーマを決めないと始まらないので、取り敢えずカンディンスキーを真似てみる
まずは横線をスーッと描いて、ドライヤーで乾かします
カンディンスキーは早々に諦めて、あとは感性のままに 笑
絵の具が乾かないうちに上塗りしてしまうと滲んでしまうし、筆圧も一定に描くのが難しい
先週末は多摩川花火大会を観に行ったのを思い出し、そのモチーフを中心に描きました
ワカケホンセイインコの群れが空を飛んでいる感じ
ちなみに下は中三の次女が描いたワカケホンセイインコ
とても可愛がっていた想い入れもあり、なかなか上手く描けている
いろいろゴチャゴチャ書き足していったら、なんか古代文明の遺跡?みたくなってきた
まあいいか
カッターで枠から画用紙を切り離します
次回はグリザイユ画法をやります(四角柱相貫体と角錐角柱相貫体)
果たして水彩画でちゃんと描けるのか?不安しかありません 笑
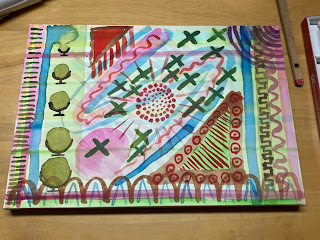



















コメント